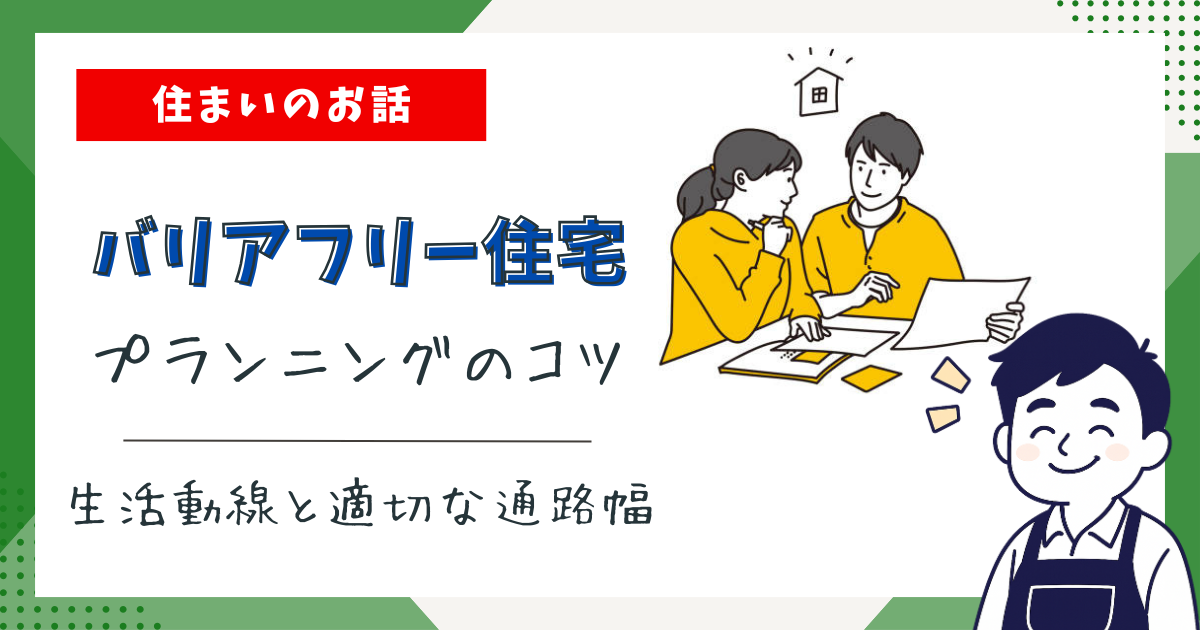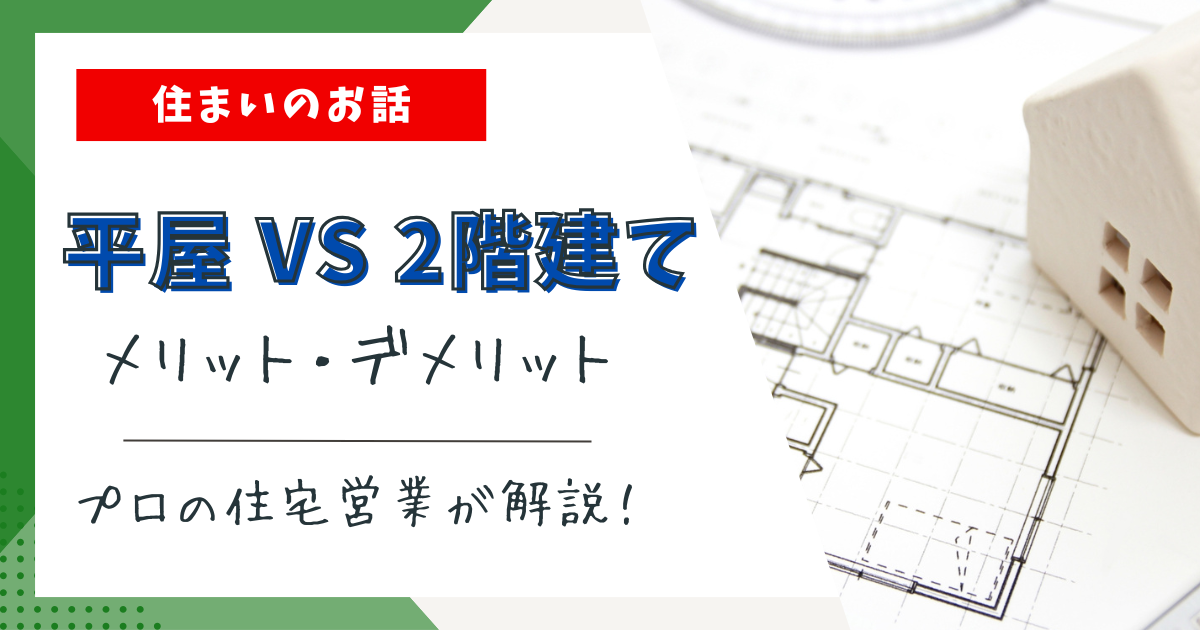【体験談あり】児童発達支援センターの利用8ステップ|申請~通所までの完全ガイド
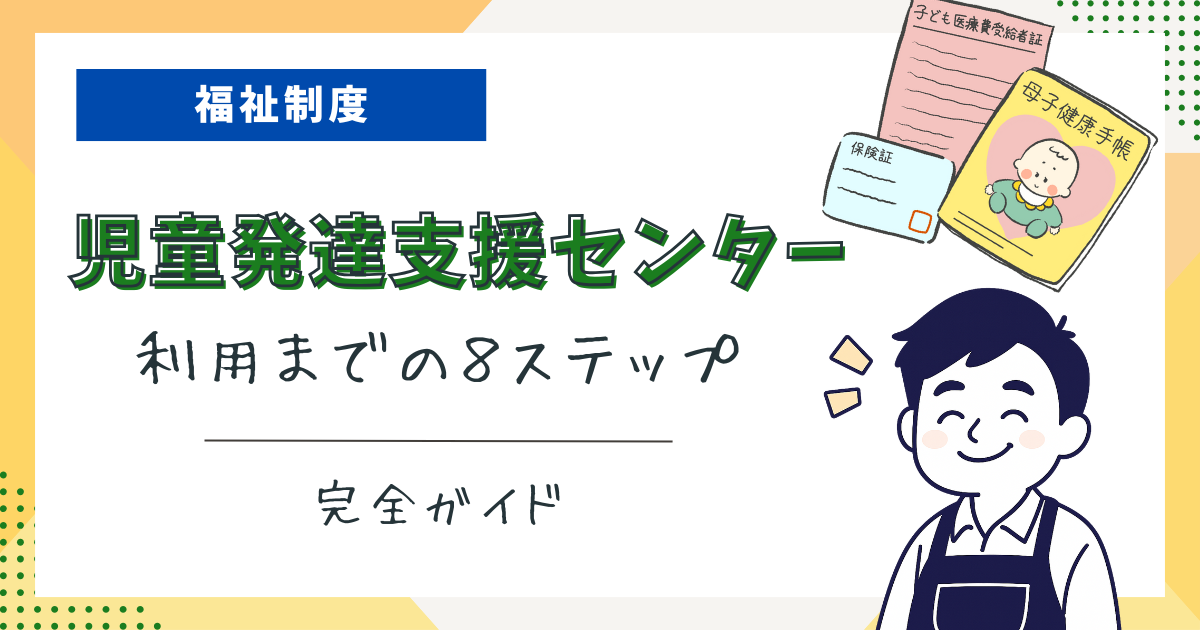

発達がゆっくりだけど大丈夫かしら…

施設を利用したいけど、何から始めていいのかわからない
私の子どもは、生まれつき障がいがありました。
「保育園にも入れないかも…」と、不安を抱えたまま漠然と過ごす毎日。
0歳の頃は“療育”という言葉すら知らず、ある日Instagramで「児童発達支援センター」や「児童発達支援事業所」の存在を知ったことが、すべてのはじまりでした。
とはいえ、そこから何をどう進めていいのか分からず、手探りの状態。
それでも少しずつ行動を重ねていき、ようやく児童発達支援センターの利用にたどり着くことができました。
基本的な流れは、
- 市区町村やセンターに相談
- 所定の手続きを経て「受給者証」を取得
- 支援施設と契約
というステップです。
でも、実際にはその合間にたくさんの“つまずき”がありました。
この記事では、児童発達支援センターを利用するまでの流れを、
わが家の実体験と厚生労働省のガイドラインに沿って、わかりやすく解説します。
児童発達支援センター・児童発達事業所とは?

児童発達支援センターって何をしてくれる場所なの?

児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違いは?

私もはじめは、全く分かっていませんでした。
ここでは、実際に子どもを通わせて感じた“リアルなイメージ”を交えながら、児童発達支援センター・事業所の役割や特徴を、できるだけわかりやすく解説します。
児童発達支援センターと児童発達支援事業所の違い

児童発達支援事業所は、発達に不安のある 0〜6 歳の未就学児が通う“通所型”の療育施設の総称です。
このうち、地域の中核的な役割を担い、巡回相談や保育所・幼稚園への支援も行う拠点的な施設が「児童発達支援センター」と呼ばれます。
児童発達支援センター・事業所は「療育」のスタート地点
言葉の遅れやコミュニケーションの困難、感覚過敏、身体の動かしづらさなど、発達の特性は子どもによってさまざまです。
センターでは、そんな子ども一人ひとりに合わせて、次のような支援が行われます。
- 日常生活のトレーニング(排泄・着脱・食事など)
- 集団行動の練習(順番を待つ、ルールを守る 等)
- 言語や発音、遊びの中での関わり方のサポート
- 感覚統合・作業療法などの専門的支援
つまり、保育園の“集団保育”とは違い、発達のペースに合わせた“個別支援”をしてくれる場所なんです。
どんな人が支援してくれるの?
支援センターには主にこのような専門スタッフがいます。
- 保育士・児童指導員
- 作業療法士(OT)
- 言語聴覚士(ST)
- 理学療法士(PT)
- 相談支援専門員
- 看護師(医療的ケア児対応のため)
※センターや事務所によっては常駐していない場合もあります
どの先生も、「発達に特性がある子ども」との関わりに慣れていて、親の気持ちにも寄り添ってくれるのがありがたかったです。

入園後の保育園や幼稚園との橋渡しをしてくれたり、困ったときにいつでも相談できるのも心の支えになります。
通い方・時間・費用は?
施設や地域によって異なりますが、主に以下のような形が一般的です。
| 項目 | 内容の一例 |
| 通所頻度 | 週1〜5日(支給量による) |
| 時間帯 | 午前・午後の半日制が多い |
| 送迎 | 事業所によって送迎あり・なしが分かれる |
| 利用料金 | 世帯年収に応じて「0円〜上限あり」 |

我が家では、1歳から週1日・午前中のみの親子通所からスタートしました。
自治体によって制度は多少違うので、必ずお住まいの市区町村の福祉課などに確認してみてください。
障がい者手帳や診断がなくても通える?
児童発達支援は、障害者手帳や医療的な診断がなくても利用できる場合があります。
その場合、自治体が発行する「障害児通所受給者証」を取得すれば利用可能です。
受給者証は、医師の診断書や意見書、または自治体の判定によって認められれば交付されます。

実際にわたしたちは主治医に意見書を書いてもらい受給者証の交付を受けました。
次の章では、「児童発達支援センターを実際に利用開始するまでの流れ」を、わが家の体験も交えて8ステップでわかりやすくご紹介します。
利用までの流れを8ステップで解説
ステップ①:市区町村や支援センターへ相談予約

まずは、お住まいの市区町村(福祉課や子ども家庭課など)に連絡し、「療育について相談したい」と伝えましょう。
この初回相談をきっかけに、児童発達支援センターや地域の相談支援機関に繋いでもらえることがあります。
その他、支援センターへ繋いでくれる相談ルートの例です。
- 乳児健診での保健師からの紹介
- 小児科や発達外来など医療機関からの紹介
- 保育園・幼稚園・こども園からの声かけ
- すでに関わっている相談支援専門員からの提案
わが家では、1つ目は大学病院の主治医から、2つ目は相談支援専門員を通じて支援センターに繋がりました。

ステップ②:初回面談(相談支援)
次は、センターや市区町村の担当者との面談です。
子どもの発達状況や家庭での様子、心配なことなどを詳しく伝えます。
ここでは、「どんな支援が必要か」「どのような施設が合っているか」を一緒に考えていきます。

今の発育段階に合わせて丁寧に提案してもらえたので、安心して話ができました。
ステップ③:医師の意見書・診断書を準備

通所を希望するには、医師の意見書または診断書が必要です。
ここで重要なのは、必ずしも“障がい名の診断”がなくてもよいという点です。「療育の必要性あり」と医師が判断すれば発行されます。
発行には数千円の費用がかかるケースが多く、作成にも時間がかかることがあるため、早めの準備が大切です。
ステップ④:事業所見学・利用先の選定
受給者証の申請前に、気になる児童発達支援センターや事業所を見学しましょう。
見学時には、以下のポイントをチェックするのがオススメです。
- 対象年齢や空き状況
- 支援内容やプログラム(療育内容)
- 送迎の有無
- 保護者の関わり方(親子通所/子どもだけ等)
- スタッフの雰囲気や子どもへの接し方
人気の施設は空き待ちになることもあるため、複数の事業所を候補に入れておくと安心です。

うちは、子どもに合ったリハビリ内容があるかと、スタッフの対応で決めました!
ステップ⑤:障害児通所受給者証の申請
通いたい施設が決まったら、市区町村に「障害児通所受給者証」を申請します。
申請は担当課から紹介された相談支援専門員がサポートしてくれます。
申請後も、支援中は1〜6ヶ月ごとに相談支援専門員の定期訪問があります。

相談支援専門員は困ったときの心強い味方です!
ステップ⑥:支給決定・受給者証交付
審査が通ると、通所可能な日数(例:週2回など)と利用料金の上限額が記載された「受給者証」が交付されます。
利用者負担は原則1割ですが、所得に応じた月額上限があり、次のように設定されています。
| 世帯区分 | 月額上限(0〜2歳児) |
| 生活保護・住民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般世帯(年収約890万円未満の世帯) | 4,600円 |
| その他の世帯(年収約890万円以上の世帯) | 37,200円 |
ステップ⑦:施設と契約・個別支援計画の作成
受給者証を持参して、施設との契約を行います。
契約後、個別支援計画(お子さま個々の特性に応じた支援方針)をスタッフと一緒に作成します。この計画は半年ごとに見直しがあります。
はじめての支援計画づくりは緊張しますが…
わが家の希望も聞いてくださり、安心してお任せできました。

ステップ⑧:通所開始!

すべての準備が整ったら、いよいよ通所スタートです!
初めは親子通所で慣らし、徐々に子どもだけの通所に切り替える家庭が多いです。
注意したいつまずきポイント

申請から通所までの間で、多くの家庭がつまずきやすいポイントをまとめました。
医師意見書の入手待ちが長い
小児神経科の予約が3か月先…。診断が出ずに手続きが進まない…。

利用を検討し始めた段階で主治医に意見書を依頼するとスムーズです!

必要書類が自治体ごとに違う
ネットの情報と、市役所の説明で言っていることが違って混乱しました…。

まずはお住まいの自治体の福祉課で、必要書類を確認してから進めると安心です。

セルフプラン作成で差し戻し
サービス等利用計画案は自分でも作れるって聞いたけど?

いわゆる「セルフプラン」でも可能ですが、差し戻しになることも…。相談支援専門員にお願いするのが安心です!

空き枠がなく利用ができない
人気の施設が満員で、いつから通えるのかわからない…。

年度末(3〜4月)は転園で空きが出る可能性も!
仮予約やキャンセル待ちの登録が効果的です。

まとめ|迷ったらまずは相談してみよう
児童発達支援センターや事業所の利用は、思い立ってすぐ始められるものではなく、準備や手続きに時間がかかります。
だからこそ、「悩んだらまず相談」が一番の近道です。
わが家も、「子どもができることを少しでも増やしたい」という思いで療育を始め、今では集団生活に慣れ、笑顔も増えました。

また、単独通所ができるようになることで、私たち親にも“心と時間の余裕”が生まれたことも大きな変化でした。
子どもの発達のペースに寄り添いながら、家族で前向きに歩んでいける環境づくりの一歩として、このガイドが参考になれば幸いです。
私のブログでは、障がい児を育てる家庭の負担を減らす時短術や、住みやすさを追求した家づくりの工夫についても発信しています。
気になるテーマがあれば、ぜひ他の記事もご覧ください。
あわせて読みたい

人気記事