【完全版】障がい児育児の医療費・助成金・補助金のまとめ


障がい児の子育てって、どれくらいお金がかかるの?
通院、リハビリ、車いすやバギー、おむつ代、装具の購入、交通費……
育児にかかる出費の多さに、不安を感じている方も多いと思います。
わが家も最初は「何にどれくらいかかるの?」「どんな制度が使えるの?」と不安でいっぱいでしたが、制度を知って申請を進めることで、想像以上に家計が助けられました。
ただし、一部には自己負担が発生するケースもあるため、注意が必要です。
この記事では、障がい児育児に実際どれくらいお金がかかるのか、どんな支援制度が使えるのかを、まとめてご紹介していきます。
申請が難しそう……と感じる方でも、
知っておくだけで不安はぐっと軽くなりますよ。

障がい児育児でかかる主な費用とは?

障がい児の育児には、医療・リハビリ・日常生活に関わるさまざまな費用が発生します。
ここでは、実体験もまじえて、主な費用を項目別にご紹介します。
障がい児にかかる費用一覧

【モデルケース】わたしの家の場合
実際にわたしの家庭でかかっている月額費用を紹介します。

- 年齢:3歳時点
- 受診科:小児科・外科・眼科 など定期通院
- 発達支援:児童発達支援事業所2カ所を併用
→ 利用料:月額上限4,600円(無償化により0円)+教材費300円 - 補装具:コンタクトレンズ・足の補装具あり
- 車椅子:バギーと座位保持椅子で生活
- 薬剤:胃ろう食(ラコール)/てんかん薬/睡眠導入剤
→ 医療費自己負担:0円(助成制度活用) - 日用品:おむつ代 0円(支援対象)
公的な医療制度や補助を使えば負担額はぐっと抑えられますよ!

意外とかからないんですね!

そうなんですよ!「まずは知ること」が安心への第一歩です。
それでは次に主な医療制度や支援制度、補助金のお話をします。
どんな支援制度があるの?

具体的にどんな支援が受けられるの?
障がい児への支援制度はおおきく3つに分けられます。
- 【助成】かかるお金の一部または全部を補助してくれるもの
- 【手当】定期的にお金がもらえるもの、補助金
- 【税制優遇】払う税金が少なくなること
障がい児への助成制度
3-1 乳幼児・子ども医療費助成制度

多くの自治体では、乳幼児(子ども)の医療費が無償化されています。
わたしの家では、通院・入院費用や薬代が無料になっています!

ただし、自己負担額や対象年齢は自治体によって異なります。詳しくは、お住まいの担当課にお問い合わせください。
3-2 発達支援センター・発達支援事業所の利用
児童発達支援センター・事業所の利用は、原則として月額4,600円の自己負担で利用可能です。
また、「3歳児~5歳児」は幼児教育の無償化*により利用料は0円になります。
月額自己負担額(0〜2歳児まで)
| 世帯の区分 | 月額上限額 |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯(※所得割28万円未満) | 4,600円 |
| それ以外(年収約890万円以上) | 37,200円 |
児童発達支援センターの利用開始までの流れはこちらの記事で紹介しています。
お子様の発達支援をご検討されているかたはご参考ください。
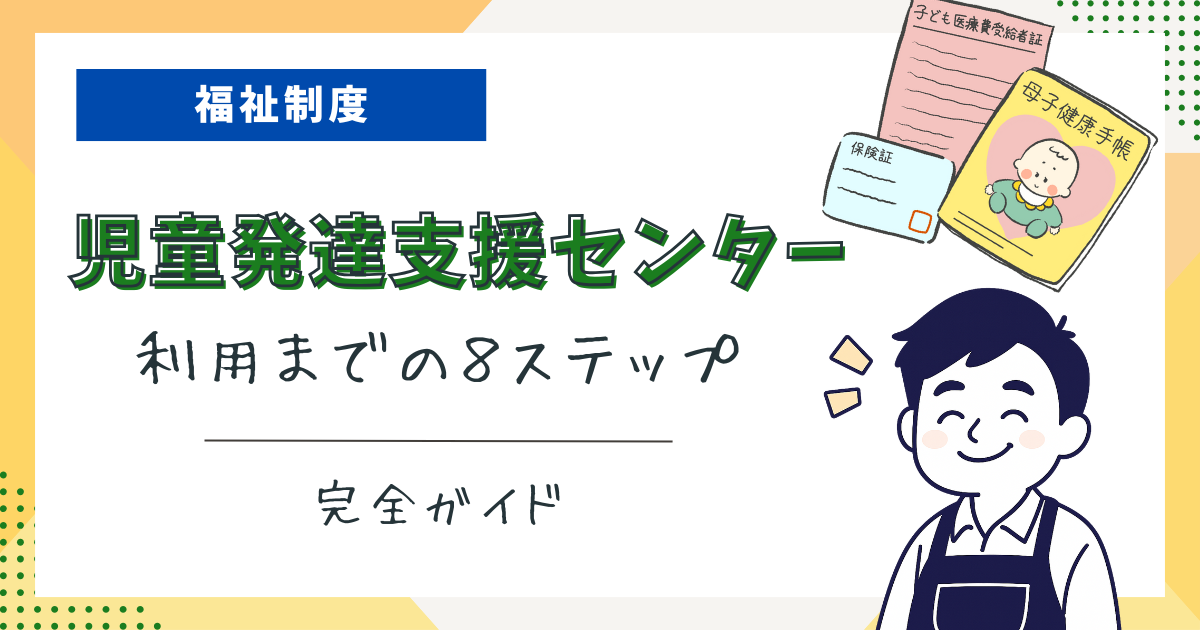
3-3 補装具費支給制度

バギー(車いす)や座位保持椅子などの購入や修理にかかる費用の一部を、公費で支給する制度です。
一般家庭の自己負担額1割(上限額:37,200円)になります。

長男が使っているバギーと座位保持椅子は同時購入をしたので、負担額は37,200円ですみました!
詳しくは厚生労働省の「補装具費支給制度の概要」をご覧ください。
また、治療用であれば健康保険からも支給が受けられます。
例えば治療用のコンタクトレンズや四肢の補装具は対象になるケースがあります。
例:治療用コンタクト代20,000円の場合
→公費で18,000円(9割)、健康保険から2,000円(1割)の補助
3-4 日常生活用具給付等事業
障がいのある方の日常生活を支援するため、入浴補助用具や紙おむつ代などを支給する制度です。
現金支給か物品支給かは自治体により異なります。
また、給付対象品目や基準額、対象者の範囲も自治体ごとに異なりますので、必ず自治体に確認をしましょう。
例:出雲市の支給対象品目
障がい児への手当・補助金制度

4-1 特別児童扶養手当
特別児童扶養手当は、20歳未満で身体や精神に重度または中度の障害がある児童を家庭で養育している父母や保護者に対して支給される国の手当です。
また障害の程度によって金額が異なり、2025年6月現在は
- 1級:月額56,800円、
- 2級:月額37,830円が支払われます。
支給は年3回(4月、8月、12月)に、それぞれ前月までの分がまとめて支払われます。
所得制限があり、一定以上の所得がある場合は支給されません。
→厚労省「特別児童扶養手当について」

所得制限には撤廃の声がありますが、実現されていません…
4-2 障害児福祉手当
障害児福祉手当は、精神または身体に重度の障がいがあり、
日常生活に常に介助が必要な20歳未満の児童に支給される手当です。
支給月額は一律16,100円です。(2025年6月現在)
毎年2月、5月、8月、11月に、前月までの合計額が支給されます。
こちらも所得制限があり、一定以上の所得がある場合は支給されません。
→厚労省「障害児福祉手当について」
障がい児子育て世帯に関係する税制優遇制度
税金の話って難しいですよね。
できるだけわかりやすく説明します!

5-1 各種障害者控除について
障がいのある方や、その方を扶養している家族に対して、所得税や住民税の控除が受けられる制度です。
※確定申告や毎年会社で行う年末調整にて申告が必要です。
控除金額
| 控除の種類 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 | 対象の例 |
|---|---|---|---|
| 障がい者控除 | 27万円 | 26万円 | 軽~中程度の障がいのある方 |
| 特別障がい者控除 | 40万円 | 30万円 | 重度の障がい(例:障がい者手帳1級など) |
| 同居特別障がい者控除 | 75万円 | 53万円 | 重度の障がい者と同居し介護している場合 |
5-2 自動車関連の減免・補助まとめ

障がい児家庭では、自動車の購入・維持に関しても減免や補助を受けられます。
私も福祉車両を購入し、自動車税36,000円・環境性能割77,300円・消費税約30万円が減免されました!

5-3 【番外編】医療費控除
医療費が多い家庭では、確定申告により税金の還付を受けられる「医療費控除」制度があります。
障がい児家庭で対象となりやすい例
- 通院のための公共交通機関の交通費
- 補装具(座位保持椅子など)の自己負担分
- その他治療にかかった自己負担分
医療費控除に関して不安な方は、事前に税務署への相談をおすすめします。
→国税庁「税に関しての相談窓口」
障がい児に子育てをしている親御さまへ
以上、障がい児の子育てに関して利用できる制度のお話をまとめました。
私自身、長男のこいたまを育てる中で使える制度を調べるのにとても苦労しました。
まとまった情報が少なく、調べるだけでも時間と労力がかかるのが現実です。
この記事が、同じように悩んでいるあなたのお役に立てれば嬉しいです。
私のブログでは、障がい児の子育てに関する悩みや疑問、役立つ情報を発信しています。
同じ境遇の親御さんが、少しでも心軽く、そして前向きに日々を過ごせるよう、これからも記事を更新していきます。
人気記事
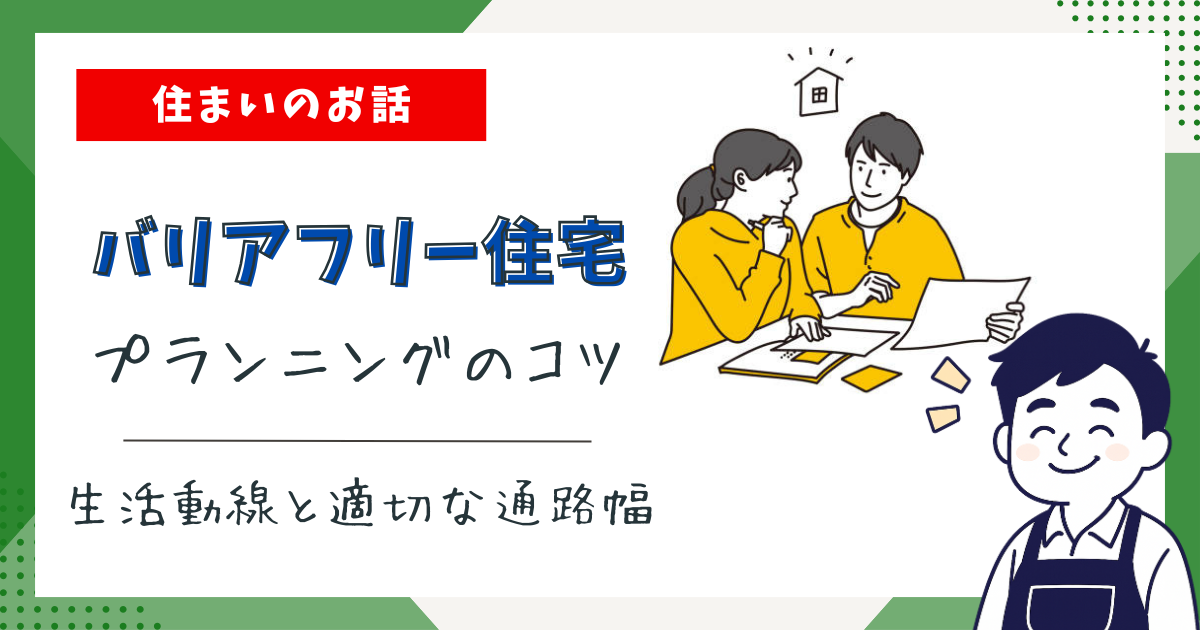

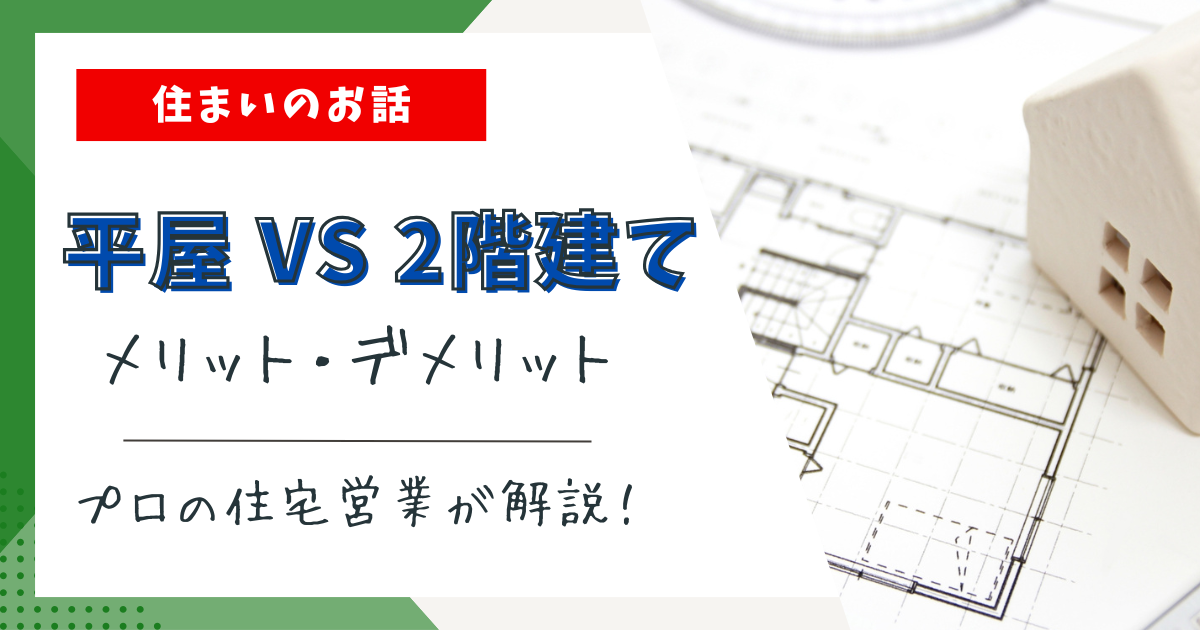






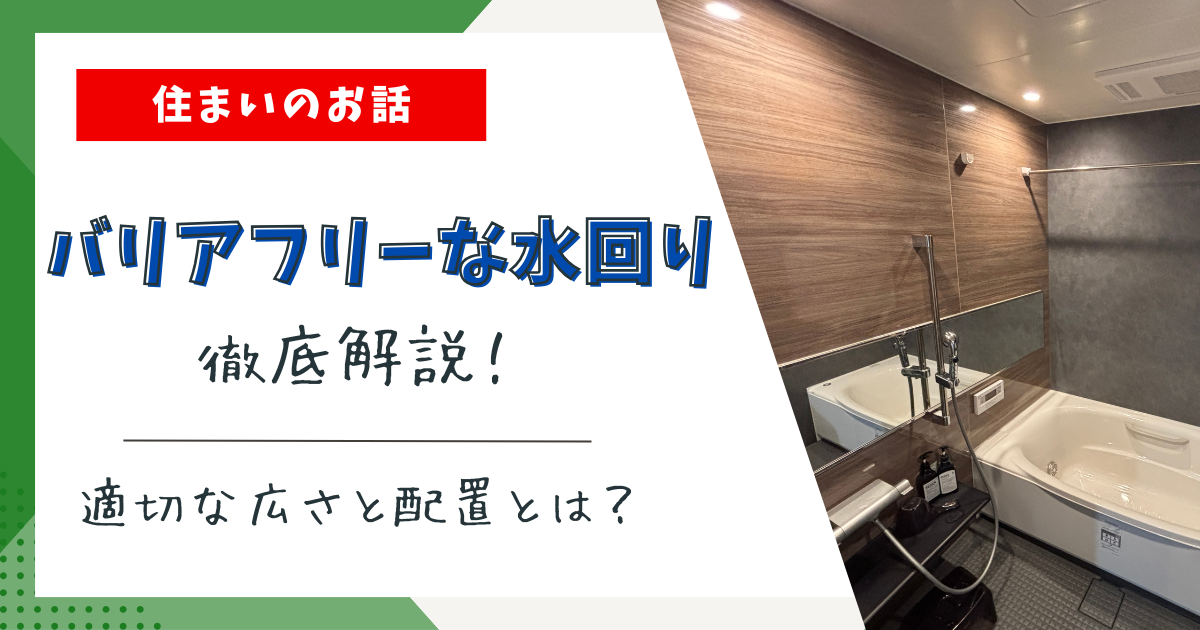
コメントを残す